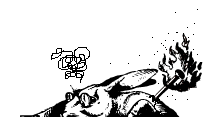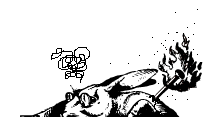ベイルートのリーダー、ザック・コンドンの音楽はしばしば、世界旅行のエキゾチックな神秘の同義語である。ベイルートの前作、2007年の『ザ・フライング・クラブ・カップ』がフランスへのラブレターを歌って以来(2009年にメキシコに立ち寄ったかのようなEP『March of the Zapotec』もあったが)、多くの人々が彼の曲が次に旅する先を尋ねてきた。多くの憶測が流れたが、『ザ・リップ・タイド』でコンドンが成し遂げた内面への旅を予見した者はほとんどいなかった。本作は、彼の始まって間もないキャリアの中でも、最も内省的でありながら記憶に残る曲の数々を収めたアルバムである。
ニューヨーク州北部とブルックリン、さらには無論のことコンドンの故郷であるアルバカーキとサンタフェでも録音が行われた『ザ・リップ・タイド』は、ベイルートにとって紛れもない飛躍点になっている。音楽的には、『March of the Zapotec』のメキシコ風フル・オーケストラの楽曲の複雑さとは対照的に、聴く者に直接訴えかけてくるハーモニーが曲に備わっている。これらの曲は、最初にピアノやウクレレで考えたちょっとしたメロディとしてはじまり、スタジオでバンド全体の貢献を得て構築されていき、最終的にはコンドンがアレンジを切り詰めて改良する過程を経て完成した。出来上がったアルバムは、刺激的なリズムがアップビートなホーンと調和しつつ、対照的に物悲しいストリングスと相俟って、ひとつのセッションで全て録音されていてもおかしくないように聴こえる。スタイルの点では、どこかの土地との直接的な帰属関係は認められない。むしろ、本作で立ち現れるのは、ベイルートでしかありえない唯一無二のスタイルであり、実はこれまでもずっと存在していたものなのだ。
歌詞の面では、コンドンは過去の単純化されたノマド的な吟遊詩人のイメージを凌駕する率直さを露にしている。曲は愛と友情と孤立とコミュニティについて語り、作り上げたお話というよりは、4半世紀を生きた若者が人生に抱く印象であるような、人間にまつわる普遍的なテーマに触れている。行ったことのない場所を想像するのでは最早なく、私たちの誰もが知りすぎているくらいによく知っている場所についての曲である。
この劇的な変化は、音楽を圧迫することなくベイルートの視野を拡げている。コンドンは、シリアスな歌詞にこれまでで最高の楽曲を覆いかぶせた。2曲目の「Santa Fe」は、彼が手がけた最良のポップ・ソングにして、彼が青年期を過ごした街に寄せた心弾む歌であり、『ザ・リップ・タイド』が「ステイケーション(遠出せずに近所や家でリラックスして過ごす休暇のこと)」の主題になっていることを早くも暗示している。とりわけ注目すべきは「Goshen」だろう。ベイルートの曲ではこれまでになかったような親密さがあり、コンドンの繊細なピアノのフレーズに包み込まれるトーチソングである。
本作は、コンドンが創始者で100%のオーナーでもあるレーベル、ポンペイ・レコードからのリリースである。ポンペイは完全にインディペンデントで、アーティスト自らが運営を行っており、『ザ・リップ・タイド』を世界中でリリースしている。この徹底したクリエイティヴ・コントロールはベイルートがこれまでも常に好んできたことだった。ベイルートのライヴは、彼らが比較的小さくてより親密な会場を選ぶために、ソールドアウトになることが多い。このファンとの直接的な繋がりが、『ザ・リップ・タイド』のリリース自体、アルバムの入手方法はもちろんのこと、自分たちの音楽のあるべき姿を100%自分たちの裁量で決めたいというバンドの強い願望にまで及んでいる。
グリフィン・ロドリゲスのプロダクションは、今回も完璧なものだ。バンドーーアコーディオンのペリン・クルーティエ、ベースのポール・コリンズ、トロンボーンのベン・ランツ、ドラムのニック・ペトリー、ホーンのケリー・プラットーーの演奏もぴったり息が合っている。ヴァイオリンのヘザー・トロスト(A Hawk and a Hacksaw)やシャロン・ヴァン・エッテンといった優れた同僚の貢献も得て、『ザ・リップ・タイド』は、聴けば聴くほどその素晴らしさを増していく。そして、そのために遠くまで旅をする必要すらないのだ。 |